▲
東ドイツのロック音楽
1989年ベルリンの壁は崩壊、そして翌年西ドイツによる東ドイツの吸収。東ドイツは世界地図から消えてしまいました。しかしながらいまだ東と西の「壁」は消えたわけではありません。ココロの中にその壁はいまだ存在しています。それが完全に消滅するのは何時のことになるのでしょうか。また、既に壁がある時代に生まれた世代、「かつて東と西はひとつの国だった」ということに実感の持てない世代は、母国を失ったことをどう考えているのでしょうか。東ドイツのロックを聴くたびにそんなことを考えてしまいます。東ドイツのロックバンドは大きく3つに分けることができます。
1つ目は、Puhdys等に代表される当局公認のバンド
2つ目は、Pankow やSandowなど、「die anderen」と称される80年代に台頭してきた一連のバンド群
3つ目は、まさしく地下で非合法的に活動をしてきたバンド群
もちろんこれらの分類は理念的なもので、現実的には個々のバンド・ミュージシャンの中でそれぞれの要素が入り混じりながら、
それぞれの個別的な状況のなかで彼らは活動していたわけです。そのような状況に関して、また東ドイツの若者文化政策に関しては、そのうちページを割いて詳しく説明する予定です。気長にお待ちください。
■cd
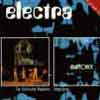 Electra/Die Sixtinische Madonna (+ Adaptionen) (1980, 1976)
Electra/Die Sixtinische Madonna (+ Adaptionen) (1980, 1976)
東ドイツ・シンフォニックロックの名盤がついにCD再発されました。このアルバムは当時東ドイツで15万枚も売れたそうです。聴きどころはもちろん一曲めのシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの壁画をテーマにした3部構成25分に及ぶ組曲です。おなじみロック楽器に加え、キーボード、フルート、クラリネット、サックス等の多彩な楽器群、そして高らかに歌い上げるヴォーカルと合唱団。牧歌的で優しげなメロディ、スリリングなアンサンブル、そしてここぞとばかりに合唱団が荘厳に盛り上げてくれます。25分があっという間に過ぎ去ります。こういう高揚感はやっぱり社会主義の得意技なんだなあと感じました。ちなみにライブ録音で、最初と最後に客の拍手と歓声 が入ってます。あと、タイトル曲の影に隠れて小曲が3曲。また、1976年発表の2ndアルバム「Adaptionen」もカップリングでお得です。こちらは、ヴォーカル無しの全曲クラシック曲のロックアレンジ集。かっこいいです。
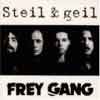 Freygang / Steil & Geil(1996)
Freygang / Steil & Geil(1996) 東ドイツアンダーグラウンドシーンの重鎮Andre Greiner-Pol率いるブルースロックバンドFREYGANG。87年にアミーガから出る予定だったアルバムが、諸般の事情でオクラ入り(「反社会主義的行為」のためAndreが逮捕されていたのがたぶん原因でしょう)。で、テープで出回っていたものがようやく1996年にCD化されたのがこれです。Die FirmaやTon Steine Scherbenのカバーも収録。Die Firmaは、Freygangが活動禁止になった時に、Andreが入ってたバンド。Die Firmaのメンバーもこのアルバムにゲスト参加してます。ちなみにFreygangは今も活動中です。
 Die Puhdys / 1+2(1974, 75)
Die Puhdys / 1+2(1974, 75)東ドイツの国家認可ロックバンドといえば絶対に忘れてはいけないプーディーズ。東ドイツロックを日本で一番早くチェックしていたのはたぶんプログレマニアで、Stern MeisenやElektra、Karatなどが早くから知られていましたが、彼らと並んで、東ドイツで長年に渡り国民的人気を誇っていたのがこのPuhdysです。今月ご紹介するのはその1枚目と2枚目のアルバムのカップリングCDです。シングルヒットした曲がずらりと並んでいます。ビートルズフォロワーバンドとして紹介されることの多い彼らですが、一聴すればすぐに分かるように70年代英国ハードロックの影響を多大に受けています。結成30年を越えてなお活躍中です。
 Feeling B / Hea Hoa Hoa Hoa Hea Hoa Hea(1989/90)
Feeling B / Hea Hoa Hoa Hoa Hea Hoa Hea(1989/90) 人に歴史あり。ドイツ産ロックで近年久々にアメリカ・ブレイクを果たしたRammstein。そのメンバーが以前在籍していたバンドがこれです。このCDは、東ベルリンの人気パンクバンドFeeling Bの自主制作アルバムに数曲ボーナストラックをつけ発売されたものです。東ドイツにもパンクバンドはあったのですよ。当時のメンバーは、 Aljosch Rompe(vo)、 Paul Landers(Gr)、Christian Flake Lorenz(key)の3人。ノイジーなギターのリフとエレピのとぼけたメロディが印象的。聴いててうきうきしてきます。LandersとLorenzは脱退してRammsteinのメンバーに。その後もFeeling BはRompe中心に活動していましたが、2000年11月23日にRompeは死去。享年53歳でした。
 Feeling B/Wir kriegen euch alle(1991)
Feeling B/Wir kriegen euch alle(1991)
feeling BのセカンドCDです。名曲「Ich such die DDR」や「Revolution 89」を収録してます。前作に比べると楽器の種類も増え(金管やら木管やら、ドゥーゼルサックも使った曲もあります)、さらに華やかな感じがします。「俺はDDRを探してるのに、それがどこにあるのが誰も知らないんだ。DDRが俺をすぐに忘れてしまうなんてとても残念だぜ!」(「Ich such die DDR」)なんて、本当の気持ちなのかアイロニーなのか分からない歌詞も興味深いです。ともあれ、89年前後の東ドイツパンクシーンはとても面白いです。
 Feeling B / Die Maske des Roten Todes (1993)
Feeling B / Die Maske des Roten Todes (1993) Feeling Bの3枚目。前作収録の「Revolution 89?」ではドゥーゼルサック等をちょっとだけ使っていましたが、それで味をしめたのか、このアルバムでFeeling Bの路線がかなり変わってしまいました。前 出のドゥーゼルサックに加え、中近東民族楽器も使用、もはやIn ExtremoやSubway to Sallyのようなトラッド色を大きく取り入れた、ト ラッド・パンクというべきものになってます。メンバーはAljoscha、Paul、Flake(Flakeは「一時的参加」との記述。製作途中で脱退のもよう)の他、民族楽器担当のゲストミュージシャンたち。 このアルバムの後どのような道を進んでいくのか興味の沸くところなのですが、Aljoschaがこの世にいない今、それもかなわぬ夢となりました。ボーナストラックが5曲。今後たどるはずだった痕跡がかすかに見え隠れします(特に13、14、15、16曲め)。
■コンピレーションcd
 Das Beste aus der DDR. 3CD-Set (1997)
Das Beste aus der DDR. 3CD-Set (1997)東ドイツ時代の国家レーベルAmigaが1997年に50周年を迎えた記念に出されたサンプラー。CD3枚のBOX仕様でそれぞれ「Rock」「Pop」「Kult」に分かれています。Rock編、Pop編ではPuhdys、Karat、Renft、Pankow など有名どころや、プログレマニアにも名が 知られているStern Meissen、Karussell、Lift、Electra、そして知らな いミュージシャンもいろいろ収録されていて楽しめます。Kult編はちょっとマニアックなヒット曲秘蔵音源を集めたもの。この3枚を聴くだけで東ドイツ時代のポピュラー音楽の様子が垣間見れるというとてもお得で重宝するCDBoxです。なお3枚ともバラ売りもされてますが、Boxで買うと60頁以上に及ぶAmigaのカタログブックレットが付いてきて、これはAmigaの主要ミュージシャンの辞典にもなっています。45DMくらいで買えるし(3000円くらい)、御購入の際はBOXをお勧めします。
 Auferstanden aus Ruinen: Der Soundtrack zur Wi(e)dervereinigung (1999)廃虚からの復活: 再/反統一のためのサウンドトラック
Auferstanden aus Ruinen: Der Soundtrack zur Wi(e)dervereinigung (1999)廃虚からの復活: 再/反統一のためのサウンドトラックタイトルから分かるように、1989年東ドイツ崩壊前後のパンクロック・コンピレーション。ずっと聴きたいと思っていましたHerbst in Peking / Bakschischrepublik や L'Attentat / Ohne Sinn が目当てで買ったのですが、その他も名曲ぞろいで堪能できます。Dritte Wahl、Sandow、Schleim-keim、Die Art、Feeling B、Die Skeptiker、Ichfunktionなど14アーチスト全18曲収録。東ドイツのパンクロックを聴いてみたいなと思う人には絶好の入門盤になるでしょう。なお副題中のWi(e)dervereinigungの(e)が、ドイツ統一に対する東ドイツの人の複雑な心情を絶妙に表わしています。
■visual
 Das Beste aus der DDR (VIDEO: PAL) (1994)
Das Beste aus der DDR (VIDEO: PAL) (1994)
東ドイツポピュラー音楽コンピレーションシリーズの番外編、ビデオ版です。当時の音楽番組やらミュージックビデオやらで、東ドイツのポップシーンを懐古します。あいまあいまにインタビューやら東ドイツロック辞典と称した用語解説(いろんなミュージシャンがそれぞれの用語について簡単に説明してくれる)などがはさまれた90分。20組以上のバンドやミュージシャンが登場。貴重映像満載です。 Volume1などと書いてますが、続きが出る気配はなし。ちょっと残念。もちろんPAL形式なので日本の普通のビデオデッキでは見れません。PAL対応のデッキで見てください
 Fluestern und Schreien: ein Rock-Report (2002)〔1988年作品:DVD:PAL:116分〕
Fluestern und Schreien: ein Rock-Report (2002)〔1988年作品:DVD:PAL:116分〕
東ドイツ末期に製作されたドキュメンタリーフィルムです。いろいろな資料にタイトルが頻繁にでてくるので、いつか観たいな〜と思ってたのですが、ついにDVDになりました。Silly、Chicoree、Feeling B、Sandowと、タイプの違う4つのバンドとそのファンをとりあげたロック・ドキュメントです。パッケージ裏には、「もはやFDJ〔※自由ドイツ青年団〕の歌や、国家公認イベント、青いシャツ〔※FDJの制服です〕を見限り、音楽と人生において自分自身の道を探そうとする世代の生活感情の表現が、ロック音楽になるのだ」と書かれてます。個人的にはFeeling Bのライブがみれただけで大満足ですが、なし崩し的に当局の若者文化政策が破綻していく80年代のロックシーンのありさまを生々しく伝える歴史的記録としても価値高いものだと思います。東ドイツの80年代末は、こんなドキュメンタリーが作られたり、ラジオ番組DT64でアンダーグラウンドバンドのデモカセットを流しはじめたりと、もはや改革の流れは止められないものだったのでしょう。DieFirmaとAndreもちょこっと登場します。その他ボーナストラックとして、SillyとDie Zoellnerのヴィデオクリップ等が収録されてます。リージョンコードは0なのですが、PALなので、PAL対応のプレーヤーでしかみれません。 パソコンなら大丈夫です。TVドキュメンタリーということなのですが、ボーナスで映画館用ポスターが収録されているので、劇場でも上映されたのだと思われます。Rammsteinファンの人にも、若き頃のFlakeやLandersをみることができ、お勧めですよ。
■book
 野村修『ビーアマンは歌う』(晶文社セレクション)1986
野村修『ビーアマンは歌う』(晶文社セレクション)1986 東ドイツの詩人であり、Liedermacher(シンガーソングライター)である、歌う詩人ヴォルフ・ビーアマン。ギターを弾きながら、がなりたてるように歌います。その詩はおしなべて体制批判的。1965年以降文学活動は禁止されます。だから歌うのです。1976年に西ドイツへの演奏旅行中、公民権を剥奪されてしまい(というより、西ドイツへの出国許可自体が、故郷追放の罠であった)、東へ帰ることができなくなりました。この本では、彼の友人でもある著者が、生い立ち、作品、活動等について語ってくれます。こういう本が日本語で、しかも日本人によって書かれるということはとてもすばらしいことだと思います。ちなみにビーアマンはニナ・ハーゲンの養父でもあります。おなじ著者による『ヴォルフ・ビーアマン詩 集』(晶文社、1971)がでてますが、現在は入手不可能。私も持ってません。ビーアマンの歌詞に関心のある方はBiermann, Wolf, All Lieder, Kiepenheuer & Witsch, Koeln, 1991 があります。文庫本程度の大きさですが、460頁を超える分量があります。
 ティモシー・ライバック『自由・平等・ロック』(晶文社)1993年
ティモシー・ライバック『自由・平等・ロック』(晶文社)1993年基本的にはロシア・東欧のロックについての本です。東ドイツのロックについては少しだけですがページが割かれており、東ドイツのロックについて日本ではほとんど紹介されてこなかったので、この本はなかなか貴重な情報を提供してくれます。ただし、共産主義による弾圧に対してロックがいかに戦ったかということがこの本のテーマであり、そのため、アジテート性の強いロックや、迫害を受けたミュージシャンのみに価値が置かれ、国家的承認を受けた者たちはほとんど評価されないという偏りはあります。訳文は直訳調で読みにくいです。
 Hintze, Goetz, Rocklexikon der DDR, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999 (ISBN:3896023039)
Hintze, Goetz, Rocklexikon der DDR, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999 (ISBN:3896023039) 東ドイツロック人名辞典。500以上のミュージシャンやバンドをアルファベット順に収録し、巻頭には東ドイツロック小史、巻末には1975年から1990年度までの「DDRヒットパレード」ベスト50の曲目を収録しています。断片的情報に頼るしかなかった東ドイツロックの情報がこの本によって一望できるようになりました。Deutschrock-Lexikonとともに必携の本と言えましょう(なおDeutschrock-Lexikonの序で出版予定されていたDDR-Rock-Lexikon は本書のことです)。総350頁で、ドイツ語です。
 Balladen, Blues & Rock-Legenden: Best of Collection - Rock und Song-Poesie Ost, Verlag Buhmann & Haeseler, 1999 (ISBN: 3927638048)
Balladen, Blues & Rock-Legenden: Best of Collection - Rock und Song-Poesie Ost, Verlag Buhmann & Haeseler, 1999 (ISBN: 3927638048)
60年代から90年代に至る東ドイツロックの歌詞と楽譜コレクションです。取り上げられている曲は100曲以上。City、Pankow、Renft、Puhdys、Veronika Fischer、Wolf Biermann、Karat、Feeling B、Sandow等々、40人(組)以上のミュージシャンの代表曲を掲載。しかも全部楽譜付き。コードもついてるし、曲によってはピアノ譜もついてます。バンドでカバーするもよし、ピアノで弾き語りするもよし。掲載されたバンド・ミュージシャンの略歴、ディスコグラフィーはもちろん、1952-1990のドイツ内外の詳細なロック関連年譜や、東ドイツの著名なポピュラー音楽研究家Peter Wickeによるエッセイ等もついてるし、さらには写真もちりばめられて、東ドイツポピュラー音楽シーンを十二分に回顧できる重宝な本です。A4ハードカバー350頁以上(9割以上が歌詞と楽譜の頁)。気になるお値段は48DMくらい。ドイツ語です。
▲musician list
▲top page
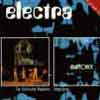 Electra/Die Sixtinische Madonna (+ Adaptionen) (1980, 1976)
Electra/Die Sixtinische Madonna (+ Adaptionen) (1980, 1976) 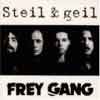 Freygang / Steil & Geil(1996)
Freygang / Steil & Geil(1996)  Die Puhdys / 1+2(1974, 75)
Die Puhdys / 1+2(1974, 75)
 Feeling B/Wir kriegen euch alle(1991)
Feeling B/Wir kriegen euch alle(1991) Feeling B / Die Maske des Roten Todes (1993)
Feeling B / Die Maske des Roten Todes (1993)  Das Beste aus der DDR. 3CD-Set (1997)
Das Beste aus der DDR. 3CD-Set (1997) Auferstanden aus Ruinen: Der Soundtrack zur Wi(e)dervereinigung (1999)廃虚からの復活: 再/反統一のためのサウンドトラック
Auferstanden aus Ruinen: Der Soundtrack zur Wi(e)dervereinigung (1999)廃虚からの復活: 再/反統一のためのサウンドトラック Das Beste aus der DDR (VIDEO: PAL) (1994)
Das Beste aus der DDR (VIDEO: PAL) (1994) Fluestern und Schreien: ein Rock-Report (2002)〔1988年作品:DVD:PAL:116分〕
Fluestern und Schreien: ein Rock-Report (2002)〔1988年作品:DVD:PAL:116分〕 野村修『ビーアマンは歌う』(晶文社セレクション)1986
野村修『ビーアマンは歌う』(晶文社セレクション)1986 ティモシー・ライバック『自由・平等・ロック』(晶文社)1993年
ティモシー・ライバック『自由・平等・ロック』(晶文社)1993年 Hintze, Goetz, Rocklexikon der DDR, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999 (ISBN:3896023039)
Hintze, Goetz, Rocklexikon der DDR, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999 (ISBN:3896023039)  Balladen, Blues & Rock-Legenden: Best of Collection - Rock und Song-Poesie Ost, Verlag Buhmann & Haeseler, 1999 (ISBN: 3927638048)
Balladen, Blues & Rock-Legenden: Best of Collection - Rock und Song-Poesie Ost, Verlag Buhmann & Haeseler, 1999 (ISBN: 3927638048)