▲
cd
その他のドイツ語ロックCD
 barbara morgenstern/FJORDEN (2000)
barbara morgenstern/FJORDEN (2000)
エレクトロニクス系の歌物ポップ。無機質的で澄んだ電子音と気の利いたノイズが、ちょっと押さえ気味の歌声やメランコリックな曲調と絡み合って美しい。音少なめでやっぱり歌がメインなのかな。たまに入るピアノや弦も効果的。こういうエレクトロ・ポップに疎い私でも、歌があってとっつき易いし、とても気に入りました。ムーグの入ってる7曲目なんか、ふわふわしていいなあ。monikaというベルリンのレーベルなのだけれど、なぜかマークが不二家のペコちゃん。最新アルパムの「NICHT MUSS」は邦盤も出たらしいけれど、未確認です。
 La Duesseldolf (1976)
La Duesseldolf (1976)
なんだろうね、この気持ちよさは。きらめくような夢見ごこちにふわふわしながらも、反復ビートが邁進して、硬質な感じが失われない。もう何も考えなくていいよ〜と言われてるような気がする。のん気だね。この容赦のない突き抜け方がいいのかな。音色のせいなのかな。Neu !の進化系、La Duesseldolfの1stアルバム。30年近くたってるのにぜんぜん古びないのはすごいね。時々妙に聴きたくなるアルバムのひとつ。
 Die Aerzte/ ディ・エルツテ (2002)
Die Aerzte/ ディ・エルツテ (2002)
おいしゃさんたち」という意味の名前のバンド。
いったい何を治療するのでしょうか。
ともかく、こいつらを紹介しなくて何がドイツ語ロックサイトだ、といわんばかりの超人気パンクバンドです。このアルバムは日本オリジナル編集の来日記念盤。近年のアルバム(「Planet Punk」「Le Frisur」「13」「Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!」)から選ばれた全22曲。ただアルバムタイトルがバンド名そのまんまって のがちょっと味気ない。せっかくですので、日本語でもっとおもしろいタイトルつけたらよかったのに・・。曲タイトル訳はいろいろ考えておもしろくつけたみたいなのにね。まあ、ともかく聴いてみてください。
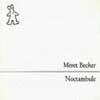 Meret Becker/ Noctambule(1996)
Meret Becker/ Noctambule(1996)以前紹介しましたメレット・ベッカーですが、その3年ほど前にもう一枚アルバムがでてました。ノイバウテンの曲にはじまり、グリム童話、マッチ売りの少女、ホレンダー、ブレヒト&ヴァイル、ジョイス、民謡、ブラームスの子守唄等々、ライブ録音なので(ベルリン?)カヴァレットの雰囲気がよく感じられます。闇の中で演じられるメルヒェンはグロテスクかつ、とても美しいです。歌詞がついていないので(わたしにとっては)聞き取るのはちょっときついですが・・・。
 Peter Hammill/Offensichtlich Goldfish:12 Songs in deutscher Sprach (1993)
Peter Hammill/Offensichtlich Goldfish:12 Songs in deutscher Sprach (1993)
ピーター・ハミルと言えば泣く子も唸るイギリス孤高の歌うたい。世界中に熱狂的ファンを持つカリスマ的
ヴォーカリストです。今でも元VDGGのメンバーとともに年に一作くらいの割合でアルバムを制作してま
す。彼関連のアルバムは多すぎて追うのはなかなか大変です。白髪が増えるとともにますます音楽性は
深みを増していきます。そのなかでも、このアルバムはちょっと変わってて、彼の80年代の歌を、ドイツの
大御所ロックミュージシャンHeinz Rudolf Kunzeがドイツ語に訳詞、それをハミルが歌ったものです。ドイ
ツ語で聴くハミルの歌もいいものです。
 Meret Becker/ Nachtmahr(1999)(メレット・ベッカー『夢魔) (PHCF3520)
Meret Becker/ Nachtmahr(1999)(メレット・ベッカー『夢魔) (PHCF3520)
メレット・ベッカーは女優として有名らしいですが、このCDを聴けば歌手としても魅力ある人だということがよく分かります。私が初めて彼女の名を知ったのは、ノイバウテン『エンデ・ノイ』収録の「ステラ・マリス」(ブリクサ・ヴァーゲルトとデュエット)でですが、このアルバムはノイバウテンのAlexander Hackeがプロデュースしてます(実は彼女の旦那)。凝りまくったサウンドに、時には幼女、時には老婆と変化自在なヴーカルが、タイトル通りの暗く重くまさに悪夢のような世界を現出させています。ライナーノートでは、ニコ、マリアンヌ・フェイスフル、ダグマー・クラウゼと並び称せられるべきシンガーだ、と誉めちぎられています。
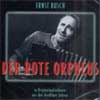 Ernst Busch/Der Rote Orpheus(1996) [録音30年代](エルンスト・ブッシュ/赤いオルフェウス)
Ernst Busch/Der Rote Orpheus(1996) [録音30年代](エルンスト・ブッシュ/赤いオルフェウス)エルンスト・ブッシュは1930年代ドイツで活躍した左翼的カヴァレット歌手。ハンス・アイスラーと組んで、数々の闘争歌を熱唱しました。闘争的な歌は勇ましく、穏やかな歌はそれっぽく優雅に歌います。彼はオペレッタの名歌手R・タウバーにちなんで、「バリケードのタウバー」とか「赤いオルフェウス」とか呼ばれていたそうです。1996年に出たこのCD「赤いオルフェウス」は、ほとんどの曲が30年代の録音で、モノラル録音だし、音もあまりよくありませんが、かえって当時の雰囲気がよく伝わって来ます。ロックというわけではありませんが、たまにはこういうのもいかがでしょう。
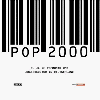 POP 2000: 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland (1999)(ポップ2000:ドイツのポップ音楽と若者文化の50年)
POP 2000: 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland (1999)(ポップ2000:ドイツのポップ音楽と若者文化の50年)1999年にドイツのTV局WDRで八夜に渡って放映された「POP 2000:ドイツのポップ音楽と若者文化の50年」というドキュメンタリー番組のサントラです。何と8枚組のCD-BOXです。レコードジャケットサイズの箱に、8枚のCDと、それに収録された音楽家達の貴重なスナップ写真がぎっしり収められたブックレット(これもレコードジャケットサイズ)が入ってます。これを聴けば、過去から現在までの(シュラーガー以外の)ドイツ産ポップミュージックの流れが一通り分かります。日本で「ジャーマン・ロック」などと言われている一連の音楽家たち(CanとかTangerine Dreamとか)と、いわゆるドイツ語ロックや、Neue Deutsche Welleなど様々な潮流は、いままで頭の中でなかなかつながらなかったのだけれど、これを聴いて、単純にドイツ産のポップということでひとつの流れのなかに置くこともできるのだなと、気づかされました。まあ、当たり前のことなんだけれど。TV番組は年度ごとに過去から現在までを追っていくという形だけど、サントラはジャンル別に再編集されてます。収録音楽家総計130組以上、130曲以上。CDはすべて70分以上びっしり収録。そのくせお値段は130DM前後というお買い得さ。
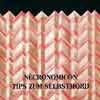 Necromonicon / Tips zum Selbstmord(1972)(ネクロノミコン/自殺の助言)
Necromonicon / Tips zum Selbstmord(1972)(ネクロノミコン/自殺の助言) ジャーマン・プログレ・ファンの間では有名なレア・アイテムでプレミアついて神格化されていたが、近年CD化されて、「なぁんだ、こんなものか」と、神秘のベール(ないしは化けの皮)がはがされてしまった悲劇のアルバムだ。知らない方がいい真実もあるのですよ。でも僕は結構好きなのだ。リズムはバタバタしてるし、埃っぽいし、ボーカルは不安定だけど、ハード・ロックを基調に、もの悲しい曲調への展開、時々入る荘厳かつ野蛮なコーラス、環境汚染やら核の恐怖やらの社会批判の歌、全体的に古ぼけた印象のサウンドだけど、混沌の70年代初頭を体現したアルバムだ(誉めてるのですよ)。2曲め「Requiem der Nature」と5曲め「In Memoriam」が白眉か。
 Dagmar Krause / Panzerschlacht(1988) [ドイツ盤]ダグマー・クラウゼ/戦車戦)
Dagmar Krause / Panzerschlacht(1988) [ドイツ盤]ダグマー・クラウゼ/戦車戦)ダグマー・クラウゼはいろんなバンドやユニット、プロジェクト、またソロでも大活躍なのですが、ここはひとつアイスラー歌曲のアルバムをご紹介。ハンス・アイスラーが誰なのか分からない人はなにかで調べてね。とりあえず有名なドイツの作曲家です。ちなみの東ドイツの国歌の作曲もしました。ダグマー・クラウゼの歌声は硬質かつ変化自在でとてもゾクゾクするほどかっこいいです。クラシック系の歌手と異なる彼女のアイスラー歌曲を体験してみてください。バックの演奏も凄みがあります。このCD、実は日本盤もありますが、そちらは英語歌詞盤で、ボーナストラックにこのドイツ語盤からいくつか収録しております。ここは両方手に入れるべきでしょう。
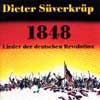 Dieter Sueverkruep / 1848: Lieder der deutschen Revolution(1998) [録音1973](ディーター・スュフェァクリュプ/ドイツ革命の歌)
Dieter Sueverkruep / 1848: Lieder der deutschen Revolution(1998) [録音1973](ディーター・スュフェァクリュプ/ドイツ革命の歌)左翼系シンガーソングライターのDieter Sueverkruepが1973年に出した名盤LPの再発CD。彼のアルバムの多くはPlaeneRecordから発売されていて、これも同レーベルからです。タイトルは「1848年:ドイツ革命の歌」。タイトル通り、収録されている曲のほとんどが、1848年当時の革命詩や風刺詩などに、Sueverkruep自身が曲をつけて歌ったものです。アコースティックギターを中心に、フルート、バイオリン、クラリネット等々の楽器が、彼の無骨ながらも表現豊かでユーモラスな歌声を控えめに盛り立て、聴くた びに味わいを感じるCDです。ブックレットには全曲の歌詞と当時の滑稽絵・風刺絵が記載されています。なおSueverkruepはFloh de Cologneの1stアルバム「Vietnam」にも参加しています。
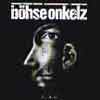 Boehse Onkelz / E.I.N.S.(1996)(ベーゼ・オンケルス/アインス)
Boehse Onkelz / E.I.N.S.(1996)(ベーゼ・オンケルス/アインス)骨太パンクロック・バンド。本アルバムでは政治批判、カトリック批判、ついでにToten Hosen揶揄やVantastisch Vier揶揄をも繰り広げている。野太く吐き出すようなヴォーカルにドイツ語のゴツゴツ感が結合し、迫力ある演奏がそれを盛り立てる。本国ではかなり人気があるバンドだ。ただ以前からネオナチの疑いがかけられているバンドで、初期のレコードは、有名なスキン・ミュージック・レーベルであるRock-o-Ramaから出ていたし、それらは歌詞が青少年健全育成上問題となるということですぐに発禁となったし(アルコール賞賛、暴力賞賛、女性蔑視、民族的差別等々の理由)、初期のライブではあからさまにトルコ人排斥のアジを叫んでいたという証言もあるし、決して根も葉もない疑惑というわけではないようだ。
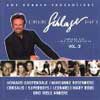 Deutsche Schlager Charts vol.2(1998)
ドイツシュラーガーチャート第2巻)
Deutsche Schlager Charts vol.2(1998)
ドイツシュラーガーチャート第2巻)
この手のシュラーガー・ヒット曲集はいろいろなものがたくさん出ているので適当に一枚聴くとどういったものがドイツでヒットしているのかが分かる。一枚紹介しておこう。これは1998年に出たもので、年に2回ほど出ているシリーズだ。Howard Carpendale、Marianne Rosenberg、Cordalis、Superboys、Leonard、Mary
Roos等々有名どころから若手にいたるまでの最新のヒット36曲が二枚組CDに収録されている。歌詞は掲載されてはいないが、ライナーは「DSC Magazin」と称して14pのミニ雑誌形式で注目音楽家のインタビューやら歴史やらを掲載している。この手のコンピレーション盤はヴォリュームの割に値段が安いのでお得だ。
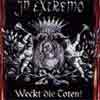 In Extremo / Weckt die Toten! (1998)(イン・エクストレモ/死者よ目覚めよ!)
In Extremo / Weckt die Toten! (1998)(イン・エクストレモ/死者よ目覚めよ!) 現代に蘇った放浪楽師を標榜するIn Extremo。このアルバムはほとんど中世の歌曲やヨーロッパのトラッドで占められているが(一曲のみオリジナル)、ロック楽器群に加え、ドゥーデルザック(ドイツ型バッグパイプ)を中心にした、シタール、シャルマイ等の民族楽器を駆使し、それら歌曲達を、HR/HM的に、マッチョに、大きく改変している。いくつか原曲を知っているものあって、その変貌ぶりに燃えるやら腰が抜けるやら笑ってしまうやら・・・。歌詞はドイツ語やラテン語など原詩をそのまま使っている。
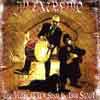 In Extremo / Die Verrueckten sind in der Stadt(1998)(イン・エクストレモ/狂人が町にいる)
In Extremo / Die Verrueckten sind in der Stadt(1998)(イン・エクストレモ/狂人が町にいる) ライブではどうなのだろうかと、同じ年に出たライブ盤「Die Verrueckten sind in der Stadt」を聴くと、これ がなんと「ロック楽器」抜きのライブ!ヴォーカル入りは一曲のみで、ドゥーデルザックを中心に軽快かつ愉快な演奏を繰り広げている。曲間の芝居気たっぷりの語りや客とのやり取りもとても楽しげで可笑しく娯楽満載。まさしく放浪楽師だ。のどかだ。当然、メタル色皆無。
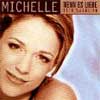 Michelle / Nenn es Liebe oder Wahnsinn(1998)(ミシェル/愛あるいは狂気)
Michelle / Nenn es Liebe oder Wahnsinn(1998)(ミシェル/愛あるいは狂気) 1975年生まれ。大御所シュラーガーKristina Bachに見出され歌手となる。近年ヒットチャートをつねに賑わしている。ちょっと都会的でちょっと田舎風味を含んだ親しみやすい旋律を持った絶妙なドイツポップスを歌っている。高音のかわいらしさと伸びのよさと切れが彼女の魅力だ。なお「今年最も成功したシュラーガーアーティスト」と書かれたシールが貼られていた。ヒット曲「Und wir wollen doch mal fliegen」収録。(2001年度のユーロヴィジョン・ドイツ代表に選ばれました)。
 Tom Angelripper / Ein schoener Tag... (1995)『トム・エンジェルリッパー/アイン・シュナー・ターク』
Tom Angelripper / Ein schoener Tag... (1995)『トム・エンジェルリッパー/アイン・シュナー・ターク』 スラッシュ・バンドSodomのリーダーによるソロアルバム。「酒」をテーマにした古いドイツ歌謡カバー曲集。アグレッシブかつパンキッシュなアレンジで、しかも曲が曲だけにいわずもがなSodomとはかなり印象の異なる陽気なアルバム。どっちかと言うとDie Roten Rosenに近い印象。なおライナーの解説はいいかげん。「[歌詞は] どうせ、どれもロクでもない内容に変えられてしまっているにちがいない(笑)」ってのはでたらめだ。私の知る限りほとんどが原曲そのままの歌詞で歌わている。また3曲ほどオリジナル曲を収録。
 Udo Juergens / Gestern-Heute-Morgen(1996)(ウド・ユルゲンス/昨日-今日-明日)
Udo Juergens / Gestern-Heute-Morgen(1996)(ウド・ユルゲンス/昨日-今日-明日) オーストリア出身の大御所シュラーガーによるセルフカバー集。ウド・ユルゲンスの大御所ぶりは日本で言うと北島三郎あたりか。50年代から90年代までの過去の名曲の数々を現在のアレンジでリメイクしつつ、新曲を交えてて彼の歌手人生をたどる一大絵巻。こてこてのドイツ・シュラーガー最良の部分がこのアルバムで聴ける。ピアノ中心のリリカルものからディスコタッチのものまで、多彩なアレンジの音の中を、彼の甘く伸びのある声が人生賛歌を歌い上げる。
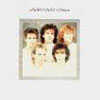 Muenchner Freiheit / Fantasie(1988)(ミュンヒナーフライハイト/ファンタジー)
Muenchner Freiheit / Fantasie(1988)(ミュンヒナーフライハイト/ファンタジー) ミュンヘン出身の5人組のバンド。シュラーガーというにはロックっぽく、ロックというにはシュラーガー。シュラーガー辞典には、「ポップとロックとシュラーガーの境界領域で成功を収めた」と書かれてある。キーボード中心の派手なアレンジに、コーラスの使用はかなりポップでさわやかで、ジャケットのイメージそのもの。歌声も線細く、さわやか。なお、昔「NHKテレビドイツ語講座」のオープニングでかけられていた「Bis wir uns wiederseh'n」を収録。
 Die Prinzen / Das Leben ist grausam(1991)(ディー・プリンツェン/人生って退屈だ)
Die Prinzen / Das Leben ist grausam(1991)(ディー・プリンツェン/人生って退屈だ) なぜかここんとこNHKラジオドイツ語講座でよく耳するDie Prinzen。今年(1999年後期)はラジオ講座の OP、EDにも使われている。アカペラコーラスを巧みに使った耳ざわりのいい音に、ヒヤリングしやすいヴォーカルに、意外と小技のきいた歌詞のせいだろうか。旧東ドイツ出身の5人組ポップグループ。デヴューした時はもはやドイツはひとつになっていた。てなわけで純粋には東ドイツのバンドとはいえないかもしれないけれど。ヒット曲「Millionaer」を始め、彼らの代表曲がいろいろ収められているこのアルバムを挙げておこう。邦盤出しても以外と売れるかも。(などと思ってたら2002年「オリ・カーン」で日本でもプチ・ブレイク。でも、その日本語ヴァージョンのみが話題となって、ゲテモノ扱い。ひどい仕打ちだ)。
 barbara morgenstern/FJORDEN (2000)
barbara morgenstern/FJORDEN (2000) La Duesseldolf (1976)
La Duesseldolf (1976) Die Aerzte/ ディ・エルツテ (2002)
Die Aerzte/ ディ・エルツテ (2002)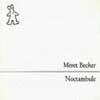 Meret Becker/ Noctambule(1996)
Meret Becker/ Noctambule(1996) Peter Hammill/Offensichtlich Goldfish:12 Songs in deutscher Sprach (1993)
Peter Hammill/Offensichtlich Goldfish:12 Songs in deutscher Sprach (1993) Meret Becker/ Nachtmahr(1999)(メレット・ベッカー『夢魔) (PHCF3520)
Meret Becker/ Nachtmahr(1999)(メレット・ベッカー『夢魔) (PHCF3520)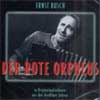 Ernst Busch/Der Rote Orpheus(1996) [録音30年代](エルンスト・ブッシュ/赤いオルフェウス)
Ernst Busch/Der Rote Orpheus(1996) [録音30年代](エルンスト・ブッシュ/赤いオルフェウス)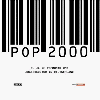 POP 2000: 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland (1999)(ポップ2000:ドイツのポップ音楽と若者文化の50年)
POP 2000: 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland (1999)(ポップ2000:ドイツのポップ音楽と若者文化の50年)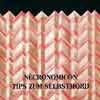 Necromonicon / Tips zum Selbstmord(1972)(ネクロノミコン/自殺の助言)
Necromonicon / Tips zum Selbstmord(1972)(ネクロノミコン/自殺の助言) Dagmar Krause / Panzerschlacht(1988) [ドイツ盤]ダグマー・クラウゼ/戦車戦)
Dagmar Krause / Panzerschlacht(1988) [ドイツ盤]ダグマー・クラウゼ/戦車戦)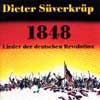 Dieter Sueverkruep / 1848: Lieder der deutschen Revolution(1998) [録音1973](ディーター・スュフェァクリュプ/ドイツ革命の歌)
Dieter Sueverkruep / 1848: Lieder der deutschen Revolution(1998) [録音1973](ディーター・スュフェァクリュプ/ドイツ革命の歌)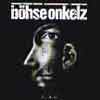 Boehse Onkelz / E.I.N.S.(1996)(ベーゼ・オンケルス/アインス)
Boehse Onkelz / E.I.N.S.(1996)(ベーゼ・オンケルス/アインス)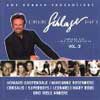 Deutsche Schlager Charts vol.2(1998)
ドイツシュラーガーチャート第2巻)
Deutsche Schlager Charts vol.2(1998)
ドイツシュラーガーチャート第2巻)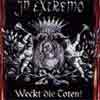 In Extremo / Weckt die Toten! (1998)(イン・エクストレモ/死者よ目覚めよ!)
In Extremo / Weckt die Toten! (1998)(イン・エクストレモ/死者よ目覚めよ!)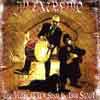 In Extremo / Die Verrueckten sind in der Stadt(1998)(イン・エクストレモ/狂人が町にいる)
In Extremo / Die Verrueckten sind in der Stadt(1998)(イン・エクストレモ/狂人が町にいる)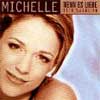 Michelle / Nenn es Liebe oder Wahnsinn(1998)(ミシェル/愛あるいは狂気)
Michelle / Nenn es Liebe oder Wahnsinn(1998)(ミシェル/愛あるいは狂気) Tom Angelripper / Ein schoener Tag... (1995)『トム・エンジェルリッパー/アイン・シュナー・ターク』
Tom Angelripper / Ein schoener Tag... (1995)『トム・エンジェルリッパー/アイン・シュナー・ターク』 Udo Juergens / Gestern-Heute-Morgen(1996)(ウド・ユルゲンス/昨日-今日-明日)
Udo Juergens / Gestern-Heute-Morgen(1996)(ウド・ユルゲンス/昨日-今日-明日)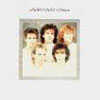 Muenchner Freiheit / Fantasie(1988)(ミュンヒナーフライハイト/ファンタジー)
Muenchner Freiheit / Fantasie(1988)(ミュンヒナーフライハイト/ファンタジー) Die Prinzen / Das Leben ist grausam(1991)(ディー・プリンツェン/人生って退屈だ)
Die Prinzen / Das Leben ist grausam(1991)(ディー・プリンツェン/人生って退屈だ)